グローバルな視点では「田園調布」に価値はない…世界の富裕層がこぞって東京の「都心」に投資するワケ
プレジデントオンライン / 2024年4月5日 8時15分
※本稿は、芦原孝充『相続の処方箋』(日刊現代)の一部を再編集したものです。
■なぜ世界の資本家は都心一等地に注目するのか
筆者は税理士の立場で、地主や企業オーナーの相続に携わってきました。
なかでも、都心一等地を利用した相続税対策を得意とし、これまでに銀座や東京駅周辺のコンサルティング実績があります。
東京駅東側の八重洲から日本橋、銀座へ続く一帯は、再開発が進みニューヨークの摩天楼のような姿になりつつあります。この地域こそ、東京の超一等地であり、今後の成長は黙っていても保証されているのではないでしょうか。
第3章では、筆者の経験をふまえ、なぜ都心の一等地なのか? その答えを読者の皆さんと考えていきたいと思います。
都心一等地は世界の資本家から、資産形成の重要な一部として注目を集め続けています。
たとえば、ニューヨークのマンハッタン島を先住民からわずか24ドルで手に入れたことや、丸の内から神田に続く一帯を三菱が坪当たり20円足らずで取得したといった話は、古くから語り継がれてきました。そしてそれらがどのような変化を遂げたかについては、ここで語るまでもありません。そうした歴史に都心一等地の将来性が裏付けられています。
■世界の経済は100年で「710倍」に成長した
ここで読者の皆さんにイメージしてもらいたいと思います。20世紀の百年に、世界の経済がどれだけ成長したかをご存じでしょうか? その速度は約1万7000倍――一方で約24倍のインフレも生じましたが、差し引き710倍ほどの成長を遂げた計算です。
経済成長≒株価の成長――株価は不動産と連動することから、ニューヨークや東京といった世界を牽引する経済の中心地では、自ずと不動産価格が上昇し、その含み益を担保に実体経済への投資を繰り返しました。これらの好循環の果実が、今日的経済繁栄となって私たちはそれを享受してきたのでした。
本章では、都心の一等地の優位性を考える、をテーマに頁を進めていきます。不動産を語るうえで、経済の浮き沈みや、それに直結するマネー・メカニズムを抜きにすることはできません。本章の前半では、最初にマネー・メカニズムを、次に失われた30年の経済衰退期を、そしてこの二つを通じて不動産についてのイメージを深めていきたいと考えています。
■信用が揺らぐとき、マネーは「紙切れ」になる
第2章では「マネーの付加価値を考える」として、マネー・メカニズムについて掘り下げました。マネーの基本を知ることは論理的思考――その眼力こそが有意な資産形成に不可欠だと考えるからです。
さて、そもそもマネーとは何か? マネーは実体経済の潤滑油として機能することに意義があります。多くの場合、マネーそれ自体を蓄えることに意義を見出している方々が多いように思いますが、マネーは単なる借用証書でしかありません。
民間の中央銀行が発行したドルや円といったマネーは、それを利用する人々の信用によって成り立っているに過ぎないのです。ですから、信用によって価値が担保されている間は、マネーはその利用価値からして不動の資産であることに変わりありません。
しかし、その信用が揺らいだときには、本来の姿である紙の借用証書へと変化してしまいます。日本においては、昭和20年に紙切れになって以降は、幸いにもそのような価値の毀損がありませんでした。約80年もの間、信用され続けてきたのです。

■「異次元の金融緩和」が日本にもたらしたもの
2013年以降、わが国では日銀の黒田総裁のもと、円の大量供給が行われてきました。それは実体経済をはるかに上回る規模のものです。
このような市場に大量の資金を供給する異次元の緩和政策は、わが国に限ったことではなく、欧米諸国を中心に競い合うようにマネーを発行し続け、その結果としてマネー価値を毀損させてきました。
たとえば、①「実体経済100対マネー100」が均衡のとれた状態であるとします。②「実体経済100対マネー1000」にマネーを増やしたならばどうなるでしょうか。①から②への変化は、マネー価値が十分の一に劣化したことを意味します。政府・日銀はそうした価値の劣化を呼び水に、実体経済に火をつけ燃焼させようと試みたのでした。
そしていま、世界ではアメリカを中心に、100→1000へと増やしたマネーの回収が始まっているのです。そのことは実体経済とマネー価値との均衡が取れる正常な状態へと巻き戻す作業なのですが、日本だけがその回収に出遅れてしまったのです。現在の円安は、そうした事象を背景に、日米の金利差と日本の貿易赤字とが相まって起きていると考えられます。
これは日本にとって非常にまずい状況です。この巻き戻しには、2013年に開始したマネー・メカニズム――日銀が国債や市場の株式を買って→円を発行する――を逆回転させることでしか達成できないからなのです。
■不動産の価格上昇と「円安」はトレードオフ
つまり、国債を爆買いし続けてきた日銀が、今度はその売り手に回ることになります。しかしいま、いわれているのは、「日銀が保有する国債の金利上昇(=国債価格低下)とそれに伴う日銀保有国債の評価損」が危惧され、少しの金利上昇が日銀の債務超過を引き起こす事態なのです。
プラザ合意を起点にした円高は、既にそのような構造的な理由によって円安傾向へ長期的転換期を迎えたと考えられるのです。
では、そうした円安傾向への変化は、日本の不動産にどのように影響するのでしょうか。
海外から見たときに、円安はバーゲンセールにほかなりません。したがって円安傾向は、外資による購買意欲を駆り立て価格の下支え効果を、そしてその結果としての不動産価格上昇に作用すると考えられるのです。
そしてもうひとつ、日本の不動産に対するそうした価格上昇圧力は、裏を返せば「円安」とのトレードオフであることもよく認識しておかなければなりません。
これらの点が、この次に続く都心と地方とを語るうえでのヒントになります。順番にそのメカニズムを追っていきたいと思います。
■経済衰退期の株と不動産
ここでは、不動産がどのようなメカニズムを背景に価格上昇を遂げてきたのかについて考えてみたいと思います。
一言でいえば、不動産の価格変化は実体経済を反映するということがいえます。戦後の日本経済の中で、不動産はその中心的存在であり続けました。
不動産は1990年にバブル経済が崩壊するまでの間、不動の地位を誇りました。不動産に対する人々の信認が揺るぎないものであった理由は、わが国の経済成長――戦後の焼け野原からスタートして、世界第二位の経済大国へ――の果実が不動産へ形を変えてきたからなのです。
戦後からバブル時までの新宿駅周辺の不動産価格は1万倍に成長したといわれました。そうした都心の不動産に牽引され、地方も同様に一定の成長軌道に乗っていったのです。
そのメカニズムは、端的には次のようなものです。実体経済の成長→株価に反映→株で得た資金が不動産に流入――株と不動産はともに連動する資産だということです。ですから、1万倍になってもなんら不思議ではありません。
1990年のバブル崩壊までの「土地神話」といわれた現象は、そうした好循環が永遠に続くと信じられてきたことを背景にします。しかし皆さんがご存じのように、バブル崩壊を機に土地神話を信じる人たちは少なくなっていきました。経済衰退が顕著になり、それが見てとれるようになったからでした。

■「会計」で経営を測定できるという思い込み
バブル崩壊後の状況について見ていきたいと思います。起点となった年は1990年です。この年はバブル崩壊とともに、東西冷戦終結による東側諸国(ロシア、中国など)の西側への市場参入が始まった年と、ほぼ重なります。これにより日本の大企業は中国への市場参入(直接投資)を始め、デフレが日本に流入し始めたのです。
はじめは、安い人件費を目当てに利益を目論んでいたのでしょう。しかし実際にはその後の長い年月をかける間に、日本は経済的にゆでガエルの状態になっていきました。プラザ合意以降の円高も相まって、中国からのデフレの輸入は、主に人件費に対する下げ圧力に作用し続けました。そのために非正規雇用を生む結果となっていったのです。

1990年以降の日本の大企業の中で、企業価値を創り出していた企業は二桁の数に過ぎませんでした。日本の企業数(法人個人を含めて)は370万社程度といわれていますが、その大部分が(利益は出ていても)価値創出の点ではマイナスであったと思います。
日本では「会計」を用いて経営を測定できるという思い込みがあるようです。虫眼鏡では野球観戦ができないように、会計は価値創出を測定する道具ではないことから、機会損失の垂れ流しを長いあいだ見過ごしてきました。
■「失われた30年」はいつまで続くのか
失われた30年を語るとき、さまざまな要因が挙げられますが、経済衰退を長期化したとどめの一発は、時を選ばず不動産を叩き売った不良債権処理でした。しかしその後、市況は持ち直したのですから、国家が強制的に不動産を処分させ、外資の手に引き渡したその理由がわかりません。
失われた30年は、残念ながらこれからも長期に続くと予想されます。それにはいくつか理由が考えられますが、ひとつは産業の新陳代謝が進まないからです。
『方丈記』の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」のごとく、価値を創出できない企業は退場し、また新たな企業が生まれていくことが資本主義経済の基本です。アメリカは軍事技術(インターネットなどIT)を民間に転用し、それが功を奏して経済を牽引したのに対して、日本は価格差異性という中世に生まれたビジネスモデルに固執し中国へ依存し続けました。
日本政府は30年もの間、一貫してその水の流れを塞きとめてきたのです。
私たちはそうした官製不況の煽りをいまも受け続けています。
本章で示す機会損失が長期に続くその根拠となるメカニズムや方程式について、詳しくお知りになりたい方は、ぜひ拙著『EVA MONEY ミリオネアの思考軸』をご一読ください。
■企業が得た利益の行き先は、3つに分類される
キーワードは「マネーは価値の低いところから高いところへ流れる」です。このシンプルな基本原理とその方程式を理解しさえすれば、ここで考えるいくつかの点がクリアになるはずです。
既に「マネーは実体経済の潤滑油」であるといいましたが、企業における利益とマネーとの関係は、次の通りです。
企業が得た利益は、会計ではいったん繰越利益剰余金に内部留保されます。そしてその利益の行き先は、次の三つに分類されます。
㋺配当せずに本業以外に投資する(本業以外に有効な活用方法がある)
㋩配当する(本業等に投資しても価値を創出できない)
この㋩「配当する」の選択は、最も非効率的な経営状態を示します。つまり、本業では儲からないから配当せざるを得ないということです――欧米のファイナンスの高等教育ではまず、配当は無能な経営者のすること、と最初の授業で教わります。
■日本企業が衰退するから不動産が選ばれる
㋺は次善の策です。つまり、本業よりも儲かる対象があり、その選択をするということです。これでは、企業経営としては本末転倒です。そして㋺のように実際に、バブル崩壊後のわが国では本業で稼げないために、大企業がこぞって不動産への投資を始めました。
それは、黒田総裁の就任以降のことでした。
では本題の、なぜ不動産が選ばれるのかについて見ていきます。
パンパンに弾けるほどの金余り――マネーの行き場がない=価値を創出する事業が日本にはほとんど存在しない――に陥った日本を代表する大企業の経済的選択は、都心の不動産に投資することでした。共通項は、どれも長期保有プレイヤーであることです。
バブル華やかなりし頃の不動産投資は、短期売買を繰り返すことで利益を得、回転率の高さが資産を膨らませました。しかし、現在の投資状況はそれとはまったく異なる特徴があります。
不動産は、長期投資こそが王道なのです。皮肉にも、人類の有史以来最も異常な低金利が正常な不動産投資を形づくったといえるのではないでしょうか。
■資産として見れば「港・中央・千代田・渋谷・新宿」
不動産は、それ自体に大きな付加価値を有するものではありますが、日本では「都心の不動産」は地方のそれと同じには語れない、そんな状況になっています。
海外の人が資産として不動産を見るとき、やはり求めるのは東京、それも港・中央・千代田といったエリア、そして渋谷・新宿のみならずターミナル駅周辺に限定されます。広げても山手線の内側、それも池袋から上野を結ぶ南側。さらに選りすぐりとなると実際には、かなり限られてしまうのではないでしょうか。
「住みたい街ランキング」の上位にランクインするような田園調布や中目黒、あるいは吉祥寺といったところに価値を見出すこともあるかもしれませんが、それは住環境のよさ、生活の利便性といった見方にしか過ぎません。
本書が定義する都心と地方は、グローバルな視点から捉えています。都心とはごく限られたエリアを指し、地方とはそれ以外を指します。たとえば、新宿を起点に中央線を下り、中野を過ぎると徐々に住宅地が広がります。こうした光景は山手線のターミナル駅から続く沿線すべてに共通することですが、これらはどれも地方(都心以外の最上位)という括りで捉えています。
しかし、「いや、そうではないだろう」というお叱りがあるかもしれませんが、ここでは本書の理解のために敢えてそのように区分しています。
■「都心」と「地方」の二極化が進んでいる
日本の国土のごく限られたエリアだけに、本書でいう特別な優位性が生じています。衰退する日本の国力を映し出すかのような、円安のトレードオフが不動産の二重構造に作用し、都心と地方とを分断するパワーが働いているからなのです。
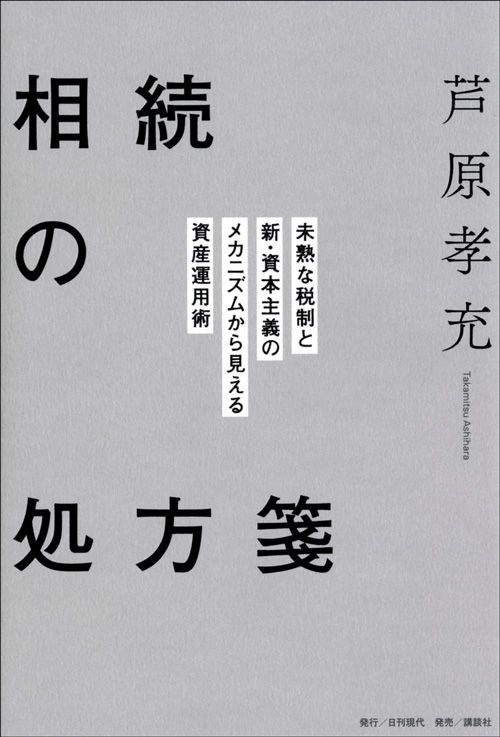
一般には、そのパワーがどれ程のものかについて見えにくいものがありますが、それは徐々に加速度をつけて現れてくると私は見ています。
不動産価格はその性質上、最終的に労働に帰結します。労働力(賃金)を担保に価格形成されていくということです。すなわち、デフレによる賃金の相対的低下は、理論的には本来的な価値と現在の取引価格との乖離に作用しているはずです。それが徐々に時間をかけて顕在化していくのではないかと思います。
日本の賃金水準はG7加盟国でも最低、お隣の韓国よりも下に位置しています。このことが、将来の地方の不動産の行方を物語っているのではないでしょうか。
----------
税理士
芦原会計事務所所長。1962年、福島県会津の酒造家に生まれる。高校進学を機に上京し、慶應義塾大学大学院商学研究科を修了(経営学・会計学専攻)。コンサルティング会社勤務を経て、1993年に東京芝で税理士開業。2007から2020年まで、拓殖大学商学部にて教鞭を執る。租税訴訟学会会員。著書に『EVA MONEY ミリオネアの思考軸』(NP通信社)がある。
----------
(税理士 芦原 孝充)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
投資家ジム・ロジャーズ「まもなくリーマンショック超の経済ショックが起きる」見逃してはいけない小さな兆候
プレジデントオンライン / 2024年5月1日 8時15分
-
相場展望4月30日号 米国株: 高金利でも米国経済は成長する 好決算発表シーズンで株価反発も、5月の経験則に注意 日本株: 「円高」「人口増」「借金減」「国力増強」政策の実行に邁進
財経新聞 / 2024年4月30日 9時41分
-
「まもなく日米株式市場の大暴落がやってくる」世界的投資家ジム・ロジャーズが予測するそのXデーはいつか
プレジデントオンライン / 2024年4月26日 16時15分
-
望月晴文・元経済産業事務次官 「日本にはヒト・モノ・カネの要素が全部揃っている」
財界オンライン / 2024年4月17日 18時0分
-
日本株上昇のウラに潜む「歴史的円安」だが…さらなる「円安進行」で株価はどうなる?【経済評論家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月13日 9時15分
ランキング
-
1今後の為替相場は…“介入でも円安の流れを変えるのは難しい”見方広がる
日テレNEWS NNN / 2024年4月30日 22時15分
-
2【参加募集告知】 『不思議の国のアリス』の世界観を香りで感じるハンドクリーム作り
Digital PR Platform / 2024年5月1日 11時5分
-
3手取り30万円・40歳の新婚男性「後悔しています」「老後資金を考える余裕はない」強い不安のワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月30日 20時0分
-
4観光業で働く人のためにも「GWは廃止すべき」 こう提言しても、何も変わらなかった理由
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月1日 6時40分
-
5テスラ、突然の充電器部門閉鎖 自動車業界に動揺
ロイター / 2024年5月1日 10時5分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










