名古屋大発ベンチャーがグーグルに唯一勝てる「自動運転技術」の切り札
プレジデントオンライン / 2020年7月10日 11時15分
※本稿は、中村尚樹『ストーリーで理解する 日本一わかりやすいMaaS&CASE』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■自動運転のカギを握る「オートウェア」
研究開発が進む自動運転技術で、カギを握るのは、自動運転に関する複数の機能を統合して制御するソフトウェアである。この分野で日本の先頭を走るのが、Tier Ⅳ(以下、ティアフォー)が開発をリードする自動運転のソフトウェア、Autoware(以下、オートウェア)だ。オートウェアは公道での本格的な利用が可能なレベルに達しており、しかもこの分野では世界で最初の、無料で使えるオープンソースとあって、各国の企業や研究機関で広く利用されている。
ティアフォーの創業者で、CTO(最高技術責任者)の加藤真平が自動運転と出会ったのは、アメリカのピッツバーグにあるカーネギーメロン大学で、研究員として情報処理を研究していたときのことだ。
「たまたま自動運転のプロジェクトに入ったのです。後にグーグルカーを作って有名になるクリス・アームソンがプロジェクトを辞めた直後だったので、猫の手も借りたいような忙しさで、ぼくもいろいろ関わることができました」
■「自動運転は危ない」という声もあるが…
そのとき加藤は、自動運転についてどう感じたのだろうか。
「一口に自動運転と言っても、実はものすごく多様な技術の集合体なのです。ある環境下で、機械学習やロボット技術ができたといっても、それだけでは実験で終わってしまいます。本当に社会に実装しようと思うと、多くのプロセスを経て、品質を保証しなければなりません。いわゆる『エコシステム』として、全体の大きなシステムを形成する必要があります。ぼくは、そこが得意なのです」
2012年に帰国した加藤は、名古屋大学にポストを得て、翌年に大学院情報科学研究科の准教授となった。
「アメリカではあんなに流行っていたのに、日本では『自動運転は危ない』とか、『使えない』とか言われて、自動運転という言葉すら使わない、自動運転NG時代でした。それが嫌で、ぼくは“自動運転”と言っていたのですが、唯一サポートしてくれたのが、武田先生でした」

名古屋大学未来社会創造機構教授で、ティアフォーの代表取締役も務める武田一哉は、「信号処理」が専門である。武田の研究する信号とは、人間の行動をカメラで撮影したり、マイクで録音したりしたデジタルデータを指す。その信号を処理することで、人間の状態を理解し、次の行動を予測することができるようになる。
■3年かけて開発した技術を「無償」で公開
研究はJST(科学技術振興機構)のプロジェクトに採択され、武田だけでなく、機械工学や画像認識、コンピューターシステム、交通工学などの研究室もプロジェクトに加わった。研究が軌道に乗り始めた2011年、モビリティに関するイノベーションを起こそうと、名古屋大学に「グリーンモビリティ連携研究センター」が設立された。加藤も、センターでの研究に合流した。
加藤は名古屋大学で、自動運転のソフトウェア作りに取りかかった。開発期間は約3年である。ロボット用のソフトウェアとして世界規模で共同開発されてきたROS(Robot Operating System)とリナックスをベースに、完全に自律して車両を制御できるレベル4のシステムを制御できる自動運転のOS(オペレーティングシステム)「オートウェア」を、長崎大学、それに産業技術総合研究所の協力を得て完成させた。

このあと加藤のとった行動が、その後のティアフォーの発展を支える基盤となる。加藤はオートウェアをオープンソース、つまりプログラムの設計図であるソースコードを無償で公開することにしたのだ。
■太っ腹な対応に隠された狙い
自動運転の開発を進める研究機関はもちろん、メーカーも営利目的で自由に使ってよく、その対価は取らない。しかも、「オートウェアを使っている」と公表する義務もないし、ティアフォー側に報告する必要もない。オートウェアに付加価値をつけて特許を取るのも自由だ。なんとも太っ腹だが、その裏には当然のことながら思惑がある。
「開発した当初、ぼくらは学生を含めて数人で開発しているのに、グーグルは何100人もの専門知識を持ったエンジニアがいました。『よーい、ドン』でやっても負けるのに、すでにグーグルはかなり先行していました。唯一、追いつき追い越せる方法が、オープンソースだったのです。ぼくらにとって良かったのは、グーグルに対しては後発でしたが、オープンソースというカテゴリーの中では、ぼくらが先駆者でした。公開した瞬間に、みんなが『待ってました』と、使い出してくれたのです」
■国内初の実験で「レベル4」をクリア
2015年には、オートウェアの提供に加え、オートウェアを使った完全自動運転システムを開発する「ティアフォー」を創業した。システムの熟度が増してきて、大学という組織の制約を離れたほうが、具体的な事業を進めやすくなったからだ。資本金の1000万円は、加藤や武田ら名古屋大の教員のほか、協力会社の社員など7人が持ち寄った。
2016年、加藤が東京大学大学院情報理工学系研究科准教授に転じると、ティアフォーの拠点は東京と名古屋の2カ所に拡大。翌2017年12月には愛知県内の一般公道で、遠隔制御型自動運転システムの実験を国内で初めて実施し、レベル4の無人運転に成功した。
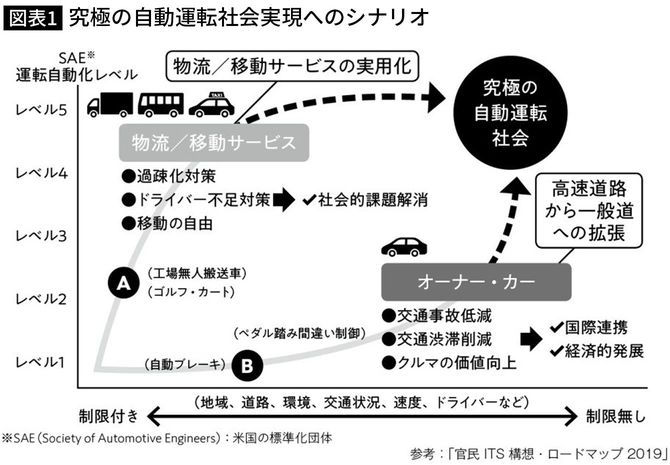
■トヨタ関連会社やインテルも参加し業界団体に成長
ティアフォーは、オートウェアの開発を加速するため、2018年に「The Autoware Foundation」(以下、オートウェアファンデーション)を作り、ライセンスをオートウェアファンデーションに譲渡した。オートウェアファンデーションにはトヨタの関連会社をはじめ、海外からはインテルやアームなど半導体大手、ベロダインなどセンサーメーカーも参加し、加藤が代表理事に就任した。それまではティアフォーという一私企業の提供するソフトウェアだったが、オートウェアファンデーションに移行したことで、業界団体としての性格を持ち、いわゆるデファクトスタンダード(事実上の標準)としての採用を働き掛けている。
こうした活動が評価され、ティアフォーの累計資金調達額は123億円に上っている。
社長の武田は、オートウェアの広まりに自信を見せる。
「オートウェアを敵だと思っている人はいないと思います。オートウェアの使えるところは全部使った上で、本当に勝負したい技術だけを自分たちで作ればいい。ソフトウェアとしてのオートウェアを、誰もなくしたいとは思っていないと思います」

■ソフトバンクの下で伸びるベンチャー企業
2019年10月、北海道の中央にそびえる大雪山の東山麓、上士幌町の公道で、自動運転の小型バスに乗客と貨物を乗せる貨客混載の実証実験が行われた。上士幌町は面積が696平方キロ。東京23区より広い。この広大な土地で公共交通を維持して行くため、上士幌町は自動運転バスの導入を目指している。2017年に実証実験を行って住民の理解を得た上で、翌2018年にはふるさと納税の仕組みを使って全国から寄付を募った。
その結果、同年4月から年末までの9カ月間で、約5300万円に上る寄付金が寄せられ、これをもとに様々な実験が行われている。一連の実験で車両の運行を担当しているのが、ソフトバンクの子会社である「SBドライブ」だ。現在は社名をBOLDLY(ボードリー)に変更している。
ボードリーは、ソフトバンクのベンチャービジネスコンテストで選ばれた佐治友基が社長を務める2016年4月に発足した会社である。

同社が最初に技術開発で取り組んだのが、自動運転バスの遠隔運行管理システム「Dispatcher」(以下、ディスパッチャー)だ。大型二輪免許を所有するスタッフが、バスと常時接続されたパソコンで運行を遠隔管理する。
■「発車時の転倒事故」をなくすために
無人で自動運転するバスには、車内と車外に数多くのカメラが設置され、乗客の人数はもちろん、乗客が座っているのか立っているのか、ドアの開閉状況や走行中の道路状況などが、リアルタイムの映像で確認できる。バスの現在位置も地図上に表示される。スピードやエンジンの回転数など、走行中の車両に関する情報も把握できる。もし車内で何らかの異常が発生したときは、アラートが鳴り、管理者はボタンひとつでバスを停車させることができる。車内の乗客と電話で会話することも可能だ。
国土交通省の調べでは、バスの車内で起きる事故でもっとも多いのが、発車時の転倒事故である。そこでディスパッチャーではAIを使って、乗客の車内移動を検知し、バスの発進時などに乗客が動こうとすると、バスはスタートしないなどの安全対策を取っている。
効率化の面では、スタッフひとりで、複数の自動運転バスを管理できるようにした。これによって、バスの運転手不足に対応でき、人件費の削減にもつながる。さらにディスパッチャーの情報は、遠隔管理しているスタッフだけでなく、自動運転車の保守点検を担当するエンジニアや、保険会社の担当者も共有することができる。
こうしたシステムに加え、「標準的なバス情報フォーマット」ファイルが用意され、事業者情報や系統、バス停などの設定を行うアプリケーション「ダイヤ編成支援システム」も開発した。
ワンマンバスでは運転手が車掌の役割も兼ねており、乗客の安全と、運行状況の確認も、当然のこととして行っている。その役割を、ディスパッチャーを活用した遠隔監視者が果たしているのだ。
■100億人を運ぶバスの時代が来るか
ボードリーはこれまで、2014年に大学発のベンチャー企業である先進モビリティが改造した日野自動車の自動運転バス、それにフランス・ナビヤ社の15人乗り自動運転バス「アルマ」を使って、各地で自動運転の実績を積み重ねている。

注目されたのは、東京電力福島第一原子力発電所内の構内バスに採用されたことだ。ハンドルや運転席のないアルマが3台導入され、ボードリーが運行支援している。
この他、羽田空港では全日空と共同で、江の島では小田急と共同して実証実験を行った。大学関係では、慶應大学の藤沢湘南キャンパスと、東京大学の柏キャンパスで実証実験を行い、企業や大学との連携も深めている。

さらに福岡県北九州市や鳥取県八頭町、長野県白馬村、静岡県浜松市などと協定を結び、自動運転の実証実験を進めている。
「乗合バスは全国6万台で、年間42億人を運んでいます。しかし1972年頃には100億人以上を運んでいた時代もありました。MaaSとCASEの時代を迎えて、もう一度、バスの輸送人員100億人の時代を目指したいですね」
佐治は、ディスパッチャーの海外への展開も狙っている。すでにアジアから引き合いが来ている。海外の新興国では、まっさらな状態から大規模なスマートシティを作るケースも多く、自動運転バスの専用レーンを確保して、日本より運行管理の仕組みを作りやすい場合もありそうだ。
----------
ジャーナリスト
1960年生まれ。NHK記者として原爆被爆者や医療問題などを取材、岡山放送局デスクを最後に独立。
----------
(ジャーナリスト 中村 尚樹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ティアフォー、高速道路トラック向け自動運転システムのリファレンスデザインを提供 2024年度より実証実験開始
PR TIMES / 2024年5月2日 11時15分
-
都市サービスの高度化に向けた『自動運転バス運行の実証実験』 及び『自動運転と新たなモビリティに関する講演会』に参画します~リニア駅を中心とした地域の暮らしと一体となった公共交通サービスの構築~
PR TIMES / 2024年4月17日 17時40分
-
聖地「斎場御嶽 (せーふぁうたき)」行きのバスを自動運転に - 沖縄県南城市とNTT西日本の挑戦
マイナビニュース / 2024年4月16日 7時0分
-
自動運転バスのレベル4実装に向けて「川崎市自動運転実装推進協議会」に参画~都市部における自動運転バスの実装を目指して~
PR TIMES / 2024年4月10日 17時40分
-
埼玉工大、入学式で自動運転スクールバスを2年連続で運行 ~新学期から、自動運転スクールバスの運行を増加し、AI技術の応用を体験する機会を拡大~
PR TIMES / 2024年4月10日 17時40分
ランキング
-
1日本郵便と西濃が共同輸送 長距離対象、24年問題に対応
共同通信 / 2024年5月6日 17時34分
-
2ドンキの“固すぎる”Tシャツがじわじわ売れている 開発者が生地の厚みにこだわったワケ
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月6日 8時0分
-
3GWが明けたら次の祝日は7月の海の日…産業医が教える「年間幸福度」を最大に引き上げる有給の賢い取り方
プレジデントオンライン / 2024年5月7日 7時15分
-
4思わずクリック「フィッシング詐欺」メールの巧妙 専門家も見極め困難、2要素認証と「意識」が大切
東洋経済オンライン / 2024年5月7日 9時0分
-
5京葉線東京駅への「長い長~~い乗り換え」回避する方法とは 実は隣の駅に秘密が!?
乗りものニュース / 2024年5月6日 15時12分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










