だからドイツは「脱原発」に突き進んだ…過激な環境左翼にドイツ政府が牛耳られている本当の理由
プレジデントオンライン / 2023年5月7日 9時15分
※本稿は、杉山大志(編集)、川口マーン惠美、掛谷英紀、有馬純ほか『「脱炭素」が世界を救うの大嘘』(宝島社新書)の一部を再編集したものです。
■巨悪に立ち向かう弱小組織というイメージだが…
2021年4月30日、独大手紙『ディ・ヴェルト』のオンライン版に、「過小評価されるグリーン・ロビーの権力」という長大な論考が載った。
綿密な取材の跡が感じられる素晴らしい論文で、久しぶりにジャーナリズムの底力を感じた。著者はアクセル・ボヤノフスキー氏とダニエル・ヴェッツェル氏。この論文には啓発されるところが多く、ドイツのエネルギー政策の謎が少し解けたような気がした。
巨悪に立ち向かう弱小な組織といったイメージの環境NGOが、実は世界的ネットワークを持ち、政治の中枢に浸透し、強大な権力と潤沢な資金で政治を動かしている実態。多くの公金がNGOに注ぎ込まれている現状。そして、批判精神を捨て、政府とNGOを力強く後押しするメディア。
本稿では、二人の著者が取材したそれらショッキングな内容を随時紹介しながら、私なりにドイツ政府の進める危ないエネルギー政策を検証してみたいと思う。
■発電の4割「石炭と褐炭」を終了させる
環境NGOは地味な草の根運動を装っているが、エネルギー政策、および地球温暖化防止政策に与える影響力という意味では、今や産業ロビーを遥かに凌いでいるという。
2011年の福島第一原発の事故の後にドイツ政府が招集した倫理委員会では、電力会社の代表や科学者ではなく、聖職者や社会学者が加わって2022年の脱原発を決めたが、7年後の2018年、脱石炭について審議するために招集された「成長・構造改革・雇用委員会」(通称・石炭委員会)では、NGOの代表者が聖職者に取って代わっていた。脱石炭を審議する会議なのに、石炭輸入組合の代表は傍聴することさえ叶わなかったというのが信じ難い。
ドイツは伝統的に石炭をベースに発展してきた国で、発電は今も4割を石炭と褐炭に依っている。長年続いたこの産業構造を、突然トップダウンで終了させるのは、かなり無謀な計画だ。性急な脱石炭は、企業の株主の権利を侵し、また、何万もの炭鉱や関連業種の労働者から生活の糧をも奪うことになる。
そこで石炭委員会は各方面への補償と影響を受ける州の産業構造改革のため、2038年までに少なくとも400億ユーロを投下するとした。今やエネルギー転換には、お金はいくらかかっても構わないというのが政府の基本方針のようだ。ただ、財源のめどは立っておらず、代替産業が何になるのかもわからない。しかし、石炭委員会のメンバーも政治家も、山積みの問題はあっさりと無視し、“遅くとも”2038年の脱石炭が決まった。
■政治とがっちり手を組んでいる
それに異議を唱えたのが緑の党で、彼らは、脱石炭の期日をもっと早めるべきだと主張した。そして、その緑の党と心を一にしているのが、ドイツ全土にもあるという自然・環境NGOだ。登録されている1100万人の会員が、今やドイツの世論形成を牛耳る一大勢力となっている。
NGOを味方につけ、脱炭素の大波に乗った緑の党は、2021年9月の総選挙後、与党入りも夢ではないと言われ始めた〈追記:同年12月に発足したショルツ政権で実際に与党入りを果たした〉。
政治とNGOのタッグはすでに堅固だ。NGOは政府の専門委員会に加わり、政治家の外遊にもしばしば同行、国際会議ではオブザーバーとして常連席を持っている。2019年、シュルツェ環境相はマドリッドでの国連気候行動サミットに出席中、「NGOの人たちとの会話は私にとって非常に重要だ。我々は同じ問題のために戦っている」とツイートした。
選挙で選ばれたわけでもない人間が税金で行動し、国政や法案の策定にまで口を挟むことについての合法性はかなり希薄だが、今のドイツではすでにそれが当たり前。しかも、そのNGOの財政を強力に支えているのが、国、州政府、そしてEUなのだ。
■巨額の予算がついても実態は「明らかな欠落部分がある」
ベルリンに本部を持つBUNDは会員58万人で、同組織が2014年から19年の6年間に公金から受けた補助の総額は、2100万ユーロ(約27.3億円)に上る。一方、ドイツ最大のNGOであるNABU(会員62万人)は、同じ期間にやはり8つの公的機関から5250万ユーロ(約68.3億円)の補助を受けた。
NABUは動植物の保護を活動の主体とし、近年は風車に巻き込まれて死ぬ野鳥の被害を訴えている。NABUの受けた補助金の内訳は、最高額3600万ユーロ(約46.8億円)が環境省からで、その他、経済協力開発省、労働社会省、教育研究省、外務省からも出た。また、それに続く2020年から2023年までの4年分の補助金としては、すでに4700万ユーロ(約61.1億円)という破格の予算が組まれている。
ただ、同論文の著者らによれば、NGOの決算報告には、「申告と実態との間に明らかな欠落部分がある」。2016年、欧州議会の予算委員会が、EUが援助しているNGOの財務監査を専門家グループに依頼したが、NGOは複雑に絡み合い、さらに、資金は環境や自然保護だけでなく、教会の慈善事業や中国との共同プロジェクトなど広範に拡散されており、結局、どのNGOが、どこで、どの活動に従事し、互いにどういう関係にあるかが掴めず、調査は徒労に終わったという。
この事実をどう解釈すべきかが私にはわからない。専門家グループが無能だったのか、NGOがプロフェッショナルだったのか、あるいは、実態を隠したい勢力が存在したのか?
■「儲かる仕事」は風車の事業者を訴えること
NGOによる疑問符のつく資金調達方法は他にもある。ドイツには現在、国民の代表として企業や自治体を訴える権限を持つNGOが78組織あるが、NABUとBUNDはその権限も存分に利用する。ディ・ヴェルト紙曰く、やり方は「実にクリエイティブ」。
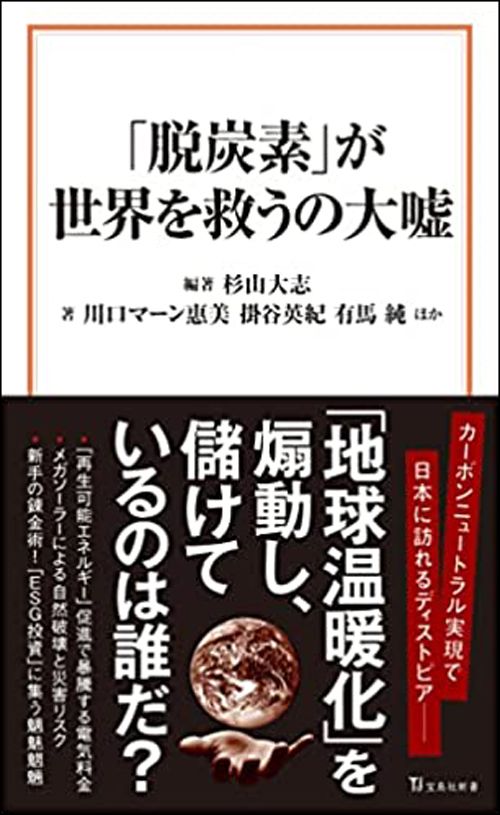
魅力的な資金調達法の一つが、風車による野鳥の被害を理由にウィンドパーク(風力発電所)の事業者を相手取って訴訟を起こすことだ。ただし、被告が原告の指定する機関に指定した金額を寄付すれば訴訟は取り下げるというから、どことなく免罪符を思い出す。いずれにせよ、これは「儲かる仕事」(ディ・ヴェルト紙)で、NABUの得意技となりつつあるという。
NABUの自然保護基金に50万ユーロ(約6500万円)を寄付したヘッセン州のウィンドパーク経営者は、「抵抗することなど、どの企業にも絶対不可能」とコメントしている。ただ、寄付した後には、鳥に優しいウィンドパークというお墨付きが与えられるそうだ。
このやり方は、しかし、NABUの内部でも問題になっており、鳥の保護と風力発電の拡大は両立できないとする会員が、風車の建設規制を訴えるNGOに移り始めているという。幹部の一人は、「我々は、今も起こっている恐ろしい野鳥の死を、過去の話だと説明している」として、NABUのプレジデントに抗議文を送りつけたという。

■壮大なエネルギー転換政策を掲げた財団の正体
環境相のシュルツェ氏もNABUのメンバーだ。日頃NGOを称賛しつつ、しかし、脱炭素達成のためには、風車は立てられる場所には隈(くま)なく立てるべきだと主張しているくらいだから、当然、風力発電事業者との距離も近い。結局、どちらからも重宝されているのがシュルツェ氏の正体かもしれない。これではNGO幹部に対する不信がますます募る。
ディ・ヴェルト紙の論考の中で、何といっても興味深かったのは、この壮大なエネルギー転換政策が、いったいどのように始まったかという点だ。それによれば発端は米国。
2007年、「勝利のためのデザイン 地球温暖化との戦いにおける慈善事業の役割」(Design To Win-Philantropy‘s Role in the Fight Against Global Warming)という研究レポートが完成した。依頼したのはヒューレット財団(ヒューレット・パッカード社の創立者の一人ヒューレットが1966年に作った慈善財団)。財団のお金をいかに活用すれば、一番効果的に温暖化防止政策を構築し、遂行できるかということが研究目的だった。
■ブルームバーグ、ロックフェラーも投資
レポートには、年間6億ドルを投資すれば、2030年までに全世界で110億トンのCO2を削減でき、地球の温度の上昇を2度以下に抑えられるということが明記された。さらに、温暖化対策をいかにして政治案件とし、国民の間に社会問題として定着させることができるか、あるいは、米国、EU、中国、インドなど、地域に特化した対策の形はどうあるべきかなどが提示された。いずれにせよ、ここで遠大な脱炭素計画にスイッチが入り、このレポートが世界のマスタープランとなったのだ。
翌2008年、ヨーロッパでこれらのプランを実行に移すため、オランダのデン・ハーグに欧州気候基金が設立された。出資者は、米国のヒューレットとパッカード両財団、ブルームバーグ、ロックフェラー、イケア財団、ドイツのメルカトル財団など。
支部は間もなくベルリン、ブリュッセル、ロンドン、パリ、ワルシャワへと拡大し、頂点にはそれぞれ、ヨーロッパの選り抜きのトップマネージャーや元政治家が、莫大(ばくだい)な報酬で引き抜かれて就任した。現在、ヨーロッパで脱炭素やエネルギー転換を謳うNGOのほとんどは、この欧州気候基金か、もう一つの巨大財団であるメルカトル財団のどちらかから、あるいは、その両方から援助を受けている。
■脱炭素の旗を掲げて皆が群がってくる
ただ、ヨーロッパでの気候政策に本当の弾みがついたのは、福島第一原発の事故の後だという。ようやく機は熟した。脱炭素の青写真を世界中に広めるのは今だ。政界、産業界、財界への浸透、新しいテクノロジーとアイデアの実践。成功は、強力な資金を持つ自分たちの手の内にあると、彼ら「Change Agents」(変革の推進者)は確信したのだろう。
以来、時は流れ、変革はその設計図どおりに進んでいる。2019年一年で、欧州気候基金とメルカトル財団が、脱炭素につながる活動をしているNGOやシンクタンクに拠出した補助金は4220万ユーロ(約54.9億円)。ちなみに、メルカトル財団の資本金は、2019年の決算報告によれば1億1650万ユーロ(約151億5000万円)。こうなると皆が、脱炭素の旗を掲げて群がってくる。

一方、この輪の中に入らず、中立な立場を維持したい研究所は、当然のことながら苦戦を強いられている。例えば、RWIのライプニッツ経済研究所は、エネルギー転換政策は、貧困層から富裕層への資本移転になると警告した。
■政府の方針と異なる研究には発注がこなくなる
また、連邦議会の専門委員会の調査でも、マックスプランク研究所の下で6つの独立した研究所が行った研究でも、再エネ法の矛盾が指摘され、その改正、あるいは廃止が進言されたが、政府はそれらを悉(ことごと)く無視した。
ゲッティンゲン大学のメディア研究者は、温暖化に関するほとんどの報道は、科学的に曖昧な部分が明確に示されていないと指摘している。問題は、政府の方針と異なる結果を出す研究には発注がこなくなることだ。こうして異端の意見は淘汰(とうた)されていく。
送電ネットワークの運営者は、今でも口を揃えて、脱原発と脱石炭を同時に行うと電力供給が保障されないと警告しているが、それについての議論は行われず、シュルツェ環境相は小型の新世代型の原発など「御伽噺」だと切り捨て、国民は、いつ商業ベースに乗るのか見当もつかない水素が、もうすぐドイツの主要エネルギーになると信じている。
■この迷走を日本人には他山の石としてもらいたい
付け加えれば、環境相は、発生したCO2を地下や海底に押し込むCCS技術も毛嫌いしており、水素は、純粋に再エネの電気で作ったグリーン水素以外は蹴っ飛ばすつもりだ。ドイツのエネルギー政策ではイデオロギーが一人歩きしている。日本人にはドイツで進行しているこれらのことを、是非とも他山の石としてもらいたい。
2023年現在、ウクライナ戦争のせいでロシアからのガスが途絶えたドイツでは、電力不足解消のため石炭ルネッサンスが起こっている。それどころか、これまで絶対にタブーだった褐炭の採掘までが復活。当然、CO2排出は急激に増えているが、CO2フリーの原発は4月15日で終了した。緑の党が与党になって以来、エネルギー政策の迷走にさらに拍車がかかっている。
ちなみにドイツの天気予報では、「明日は全国的に晴れのよいお天気」という表現が消えた。気候変動で旱魃(かんばつ)が起こっているのだから、晴れがよいお天気であるはずはない! なんだか不思議な国である。
----------
キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
東京大学理学部物理学科卒、同大学院物理工学修士。電力中央研究所、国際応用システム解析研究所などを経て現職。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)、産業構造審議会、省エネルギー基準部会、NEDO技術委員等のメンバーを務める。産経新聞「正論」欄執筆メンバー。著書に『「脱炭素」は嘘だらけ』(産経新聞出版)、『中露の環境問題工作に騙されるな!』(かや書房/渡邉哲也氏との共著)、『メガソーラーが日本を救うの大嘘』(宝島社、編著)、『SDGsの不都合な真実』(宝島社、編著)などがある。
----------
----------
作家
日本大学芸術学部音楽学科卒業。1985年、ドイツのシュトゥットガルト国立音楽大学大学院ピアノ科修了。ライプツィヒ在住。1990年、『フセイン独裁下のイラクで暮らして』(草思社)を上梓、その鋭い批判精神が高く評価される。2013年『住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち』、2014年『住んでみたヨーロッパ9勝1敗で日本の勝ち』(ともに講談社+α新書)がベストセラーに。『ドイツの脱原発がよくわかる本』(草思社)が、2016年、第36回エネルギーフォーラム賞の普及啓発賞、2018年、『復興の日本人論』(グッドブックス)が同賞特別賞を受賞。その他、『そして、ドイツは理想を見失った』(角川新書)、『移民・難民』(グッドブックス)、『世界「新」経済戦争 なぜ自動車の覇権争いを知れば未来がわかるのか』(KADOKAWA)、『メルケル 仮面の裏側』(PHP新書)など著書多数。新著に『無邪気な日本人よ、白昼夢から目覚めよ』 (ワック)、『左傾化するSDGs先進国ドイツで今、何が起こっているか』(ビジネス社)がある。
----------
----------
筑波大学システム情報系准教授
1970年大阪府生まれ。93年東京大学理学部生物化学科卒。98年東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士課程修了。博士(工学)。通信総合研究所(現・情報通信研究機構)研究員を経て、現職。専門はメディア工学。NPO法人「言論責任保証協会」代表。著書に『学問とは何か 専門家・メディア・科学技術の倫理』『学者のウソ』など。近著に『「先見力」の授業』(かんき出版)がある。
----------
----------
東京大学公共政策大学院特任教授
1982年、東京大学経済学部卒業、同年、通商産業省(現経済産業省)入省。IEA(国際エネルギー機関)国別審査課長、資源エネルギー庁国際課長、同参事官などを経て、JETRO(日本貿易振興機構)ロンドン事務所長兼地球環境問題特別調査員。2015年8月より東京大学公共政策大学院教授、2021年4月より同大大学院特任教授、現職。著書に『私的京都議定書始末記』(2014年10月、国際環境経済研究所刊)、『地球温暖化交渉の真実 国益をかけた経済戦争』(2015年9月、中央公論新社刊)、『精神論抜きの地球温暖化対策 パリ協定とその後』(2016年10月、エネルギーフォーラム刊)、などがある。
----------
(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 杉山 大志、作家 川口 マーン 惠美、筑波大学システム情報系准教授 掛谷 英紀、東京大学公共政策大学院特任教授 有馬 純)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
日本の解き方 石炭火力は廃止しかないのか? 欧米にはない日本の新技術でCO2を抑制可能、エネルギーの安定供給優先を
zakzak by夕刊フジ / 2024年5月10日 6時30分
-
脱炭素へ、エネ基本計画月内着手 35年度以降の電源構成焦点
共同通信 / 2024年5月1日 18時38分
-
脱炭素技術の開発提言 諮問会議で民間議員
共同通信 / 2024年4月19日 21時40分
-
EVと太陽光の「エコ政策」を続ければ日本は滅ぶ…日本人をどんどん貧しくする「グリーン成長戦略」のウソ
プレジデントオンライン / 2024年4月16日 9時15分
-
「NO原発、YES風車」で経済はマヒ状態…日本を抜いた「経済大国ドイツ」で企業脱出が相次いでいる理由
プレジデントオンライン / 2024年4月14日 8時15分
ランキング
-
1「日本国債」の紙くず化がとまらない…雪だるま式「借金地獄」から日本が抜け出せない根本原因【経済のプロが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月11日 11時15分
-
2コーヒー豆高騰の背景に…中国でブーム“悪魔のフルーツ”、ピザや火鍋にも【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月10日 21時10分
-
3朝ドラ登場の食堂モデル、岐阜の五平餅店が閉店へ…「寂しい」全国から名残惜しむファン足運ぶ
読売新聞 / 2024年5月10日 15時8分
-
4ヨーカドーの跡地が「世界最大級の無印良品」に…過疎地の商業モールを復活させた「社会的品揃え」の魅力
プレジデントオンライン / 2024年5月11日 9時15分
-
5【閉園騒動から再出発】「ラブライブ!聖地」水族館、新社長が語った苦悩「従業員は大量解雇」「マイナスからのスタートです」
NEWSポストセブン / 2024年5月10日 19時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










